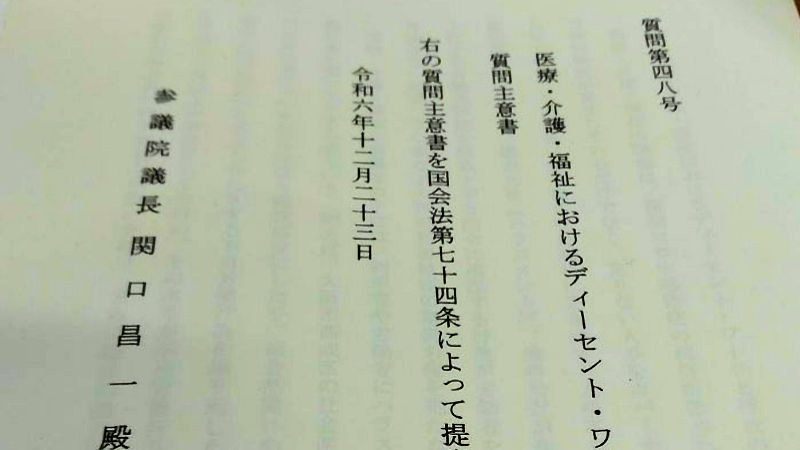(ケアワーカーズユニオン山紀会支部ブログより転載)
社民党の参議院議員大椿ゆうこさんが、山紀会支部をはじめ介護現場で働く労働者がかかえる切実な問題について、国に質問主意書を提出してくださいました。以下は山紀会支部ブログからの転載です。
=====山紀会支部ブログより転載==========
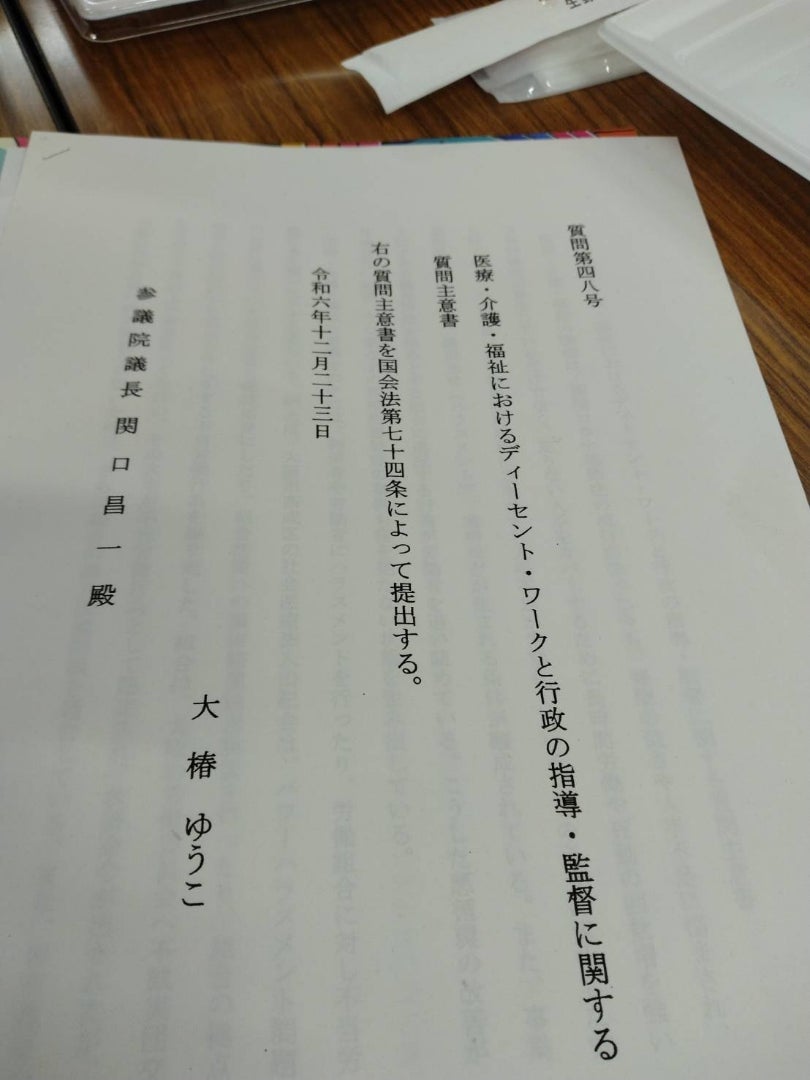
この度、社民党の大椿ゆうこさんが、ケアワーカーズユニオン山紀会支部や介護現場の問題を「医療・介護・福祉におけるディーセント・ワークと行政の指導・監督に関する質問主意書」として国会へ提出してくれました!!
その中で、社会医療法人山紀会による長年に亘る組合潰し、組合活動への懲戒処分やスラップ訴訟、不当労働行為として命令を受けても態度を改めずに組合拠点を閉鎖させようとする実態について、堺市重症心身障害者(児)支援センター・ベルデさかいによる、職場で横行する虐待や違法行為を公益通報等した結果、自宅待機、配置転換、解雇を命ぜられた労働者が適応障害を発症し、労働基準監督署が労働災害を認定させたことなどが取り上げられました!
主意書のポイントとしては、国は、市町村に対して業法違反、事業者のハラスメント、不当労働行為に関して、もっと監督・指導の権限を持たせろ!という点です。
大椿さんをはじめ、みなさんには、本当に感謝しています!みんなであきらめずにがんばりましょう!
■詳しくは以下です。
第216回国会(臨時会)
質問主意書
質問第四八号
医療・介護・福祉におけるディーセント・ワークと行政の指導・監督に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
二〇二四年十二月二十三日
大椿 ゆうこ
参議院議長 関口 昌一 殿
医療・介護・福祉におけるディーセント・ワークと行政の指導・監督に関する質問主意書
医療・介護・福祉の職場は、新型コロナ感染症の流行が去った今も、報酬の低さや人手不足に悩まされ、所得の格差が発生しているだけでなく、足りない人手をカバーするために長時間労働や夜勤の回数増を強いられている。その結果、新規採用者は職場に定着せず、人手不足が常態化している。このように劣化した労働環境では、いじめ、嫌がらせ(ハラスメント)、虐待などが生まれる条件が醸成されている。また、事業主による労働基準法を始めとする法令に違反する行為が労働者を追い詰めている。こうした悪循環の改善が見通せない結果、うつ病などの精神疾患発症の事例も後を絶たない状態を生み出している。
医療・介護・福祉の事業者の中には、利用者や労働者にハラスメントを行ったり、労働組合に対し不当労働行為を働いたりする者もいる。例えば、大阪市西成区の社会医療法人山紀会は、パワーハラスメント問題の相談に乗っていた組合役員を懲戒処分にしたり、組合活動への損害賠償請求訴訟を行ったり、組合の拠点職場を他の部門から孤立させたりする不当労働行為を繰り返した。組合は、大阪府労働委員会へ不誠実団交を含めて十件以上の救済申立てを行い、その大半が不当労働行為として認定され、救済命令が出されたが、山紀会は組合員への不利益な取扱いを続け、さらに組合の拠点職場閉鎖を通告している。また、堺市重症心身障害者(児)支援センター・ベルデさかいでは、職場で横行する虐待や違法行為を公益通報等した結果、自宅待機、配置転換、解雇を命ぜられた労働者が適応障害を発症し、労働基準監督署が労働災害を認定した。
前記の実態を踏まえ、医療・介護・福祉の仕事が、他の業種・産業とともに「働きがいのある人間らしい仕事」となり、「生きがいを持って安心して働く」ことができる就業環境になることを願って以下質問する。
一 二〇一八年のいわゆる働き方改革関連法の成立により改正された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下「労働施策総合推進法」という。)は、「職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等」を定め、職場のハラスメント対策に関する国、事業主及び労働者の責務を定めている。働き方改革関連法は、施行後五年の見直しの時期を迎えているが、過去五年のハラスメント防止策について、政府はどのように評価しているか示されたい。また、今後どのような見直しを検討し、法制度の充実を図るのか、政府の見解を示されたい。
二 労働施策総合推進法第三十条の二第一項は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めている。また、第三十条の三は、優越的言動問題について、「国は、(中略)事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。」と定めている。
医療・介護・福祉の職場は、多様な資格を持った多様な職種間の協働によって成り立っており、各職種間の職能・権限が入り組んでいるため、業務上の指揮命令系統、労務管理及び労働慣行が技術の進歩や時代の変化にそぐわないものになっていることもある。このような理由により、「優越的な関係」、「業務上必要かつ相当な範囲」について、職種や経験の違いで認識に相違が生じる場合がある。医療・介護・福祉の職場は、各職種・職務間の助言や相互批判・相互理解を含めた緊密な報告・連絡・相談による連携が常に求められる職場である。そのため、とりわけ事業者は、「優越的言動問題」を世間一般に言う「いじめ・嫌がらせ・仲間外れ」と混同してはならない。また、危険回避や業務向上等のため、業務遂行上行われる批判や指摘をハラスメントと峻別することで、労働者が職場で発言しやすく、生きがいを持って安心して働ける環境を作らなければならない。
以上の性質に鑑みれば、医療・介護・福祉の職場における具体的な事例を集約した、啓発や研修に真に役立ち、教育的に有効なガイドブック等の作成が求められていると考えるが、国として作成する考えはあるか示されたい。あるいは、事業者等に作成を促す考えはあるか示されたい。
三 職場においてハラスメントを行う事業者は、労働者の権利に関する認識が希薄で、労働組合との団体交渉に応じなかったり、組合活動を行った労働者に不利益な取扱いを行ったりする者も少なくない。ハラスメント防止のためには、労働者の権利、とりわけ労働三権に関する事業者の認識を改善する必要があると考える。しかし、労働施策総合推進法第一条では、労働者の権利の保護を目的として規定されていない。その結果、同法はハラスメントの背景にある事業者の認識不足や労使関係の非対称性について十分に対処できていないのではないかと懸念するが、政府の見解を示されたい。
四 医療・介護・福祉の職場における労使間の対立は、利用者へのサービスに悪影響を及ぼす。労使間の対立が争議状態に発展すれば、真っ先に被害を受けるのは、患者、利用者であるため、労働者は団体行動を起こすことに自制的になる。一方、前記で指摘したように、不当労働行為を働き、都道府県労働委員会の救済命令にも従わないような事業者も存在するため、行政による監督・指導を強化する必要があると考える。地方公共団体は、医療・介護・福祉に係る許認可の権限を持っており、かつ国民健康保険及び介護保険の保険者でもあるため、業法違反のみならず、事業者のハラスメントや不当労働行為に関しても監督・指導の権限を持つべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。